症候
神経・精神 (12)
1.
1.
意識障害
┗ 意識障害・譫妄の精査
2.
譫妄
3.
失神
4.
頭痛
5.
めまい
┗ 末梢性めまい
6.
複視
7.
運動麻痺・筋力低下
┗ 一肢に限局した筋力低下
┗ 四肢麻痺・対麻痺
┗ 多発単神経炎
┗ 片麻痺
┗ 四肢筋力低下
8.
しびれ
┗ ① 一肢に限局した感覚障害(単神経障害)
┗ ② 手袋靴下型感覚障害(多発神経障害)
┗ ③ 多発単神経炎
┗ ④ 脊髄・馬尾の障害
┗ ⑤ 大脳・脳幹の障害による感覚障害
9.
ふるえ
10.
認知障害
┗ 認知障害の鑑別診断
┗ Lewy小体型認知症の中核症状
┗ 意味性認知症の言語能力の問題
┗ 前頭側頭型認知症の行動障害
┗ 進行性非流暢性失語の言語症状
11.
不眠症
┗ 睡眠障害の原因となりうる疾患の検索
┗ 原発性不眠症の診断と睡眠薬の処方
複視
複視
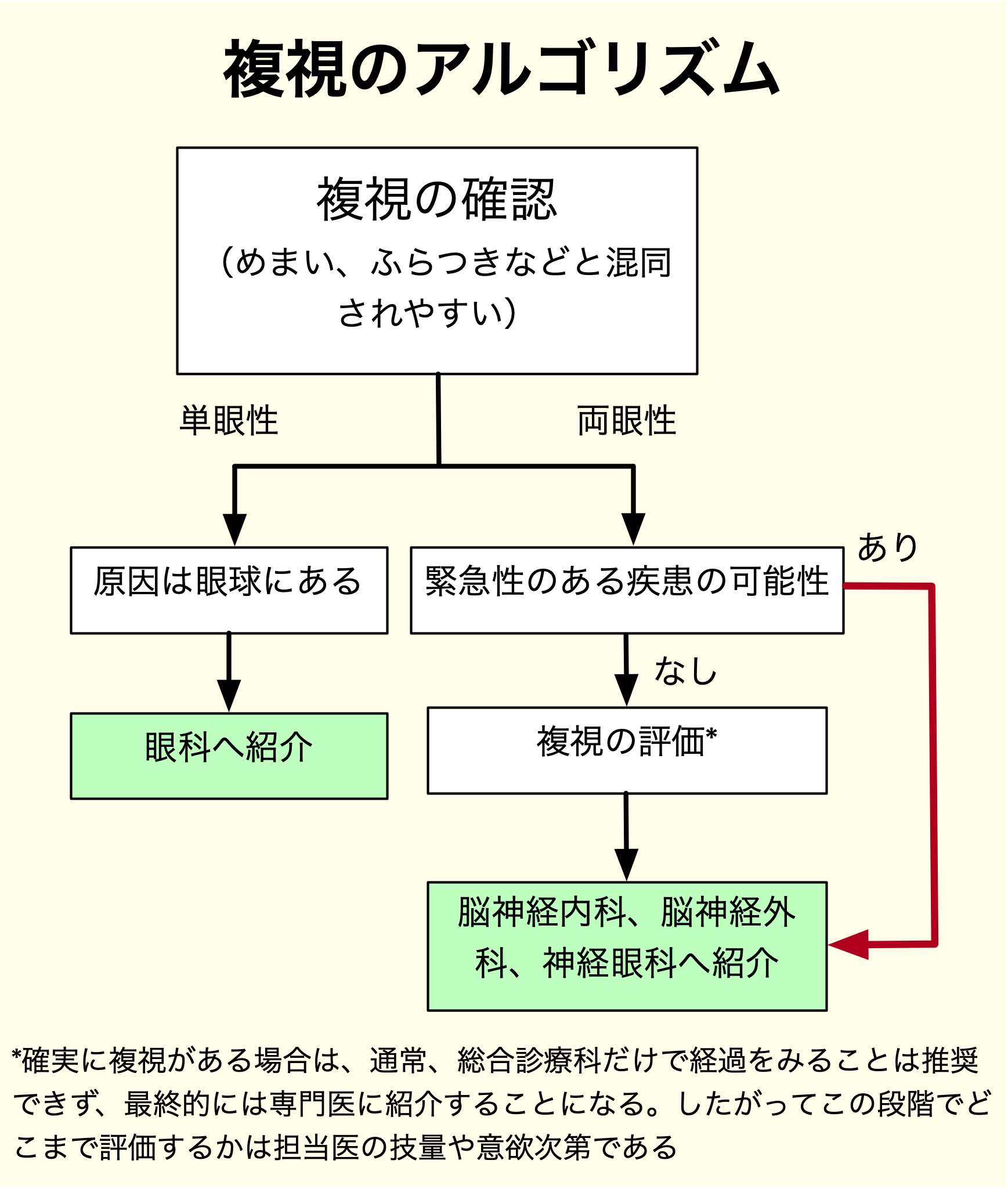
【STEP1】「複視」の確認
-
・複視とは物が二重に見えることである
・複視は、「めまい」や「ふらつき」と表現されることも多い。丁寧に問診して確認する
【STEP2】単眼性か両眼性かの確認
① まず、両眼を片目ずつ閉じてもらい複視があるかを確認
② 次に、検者が片目ずつ隠しても複視が残るかを確認する
・これで複視が残っていれば、眼球自体に問題があることを示すので眼科に紹介する
・屈折異常の矯正不良であり、角膜疾患や白内障でみられる
・これで複視がなくなれば、眼位の異常であり、外眼筋、神経筋接合部、支配神経のいずれか1つ以上の問題があることを示す
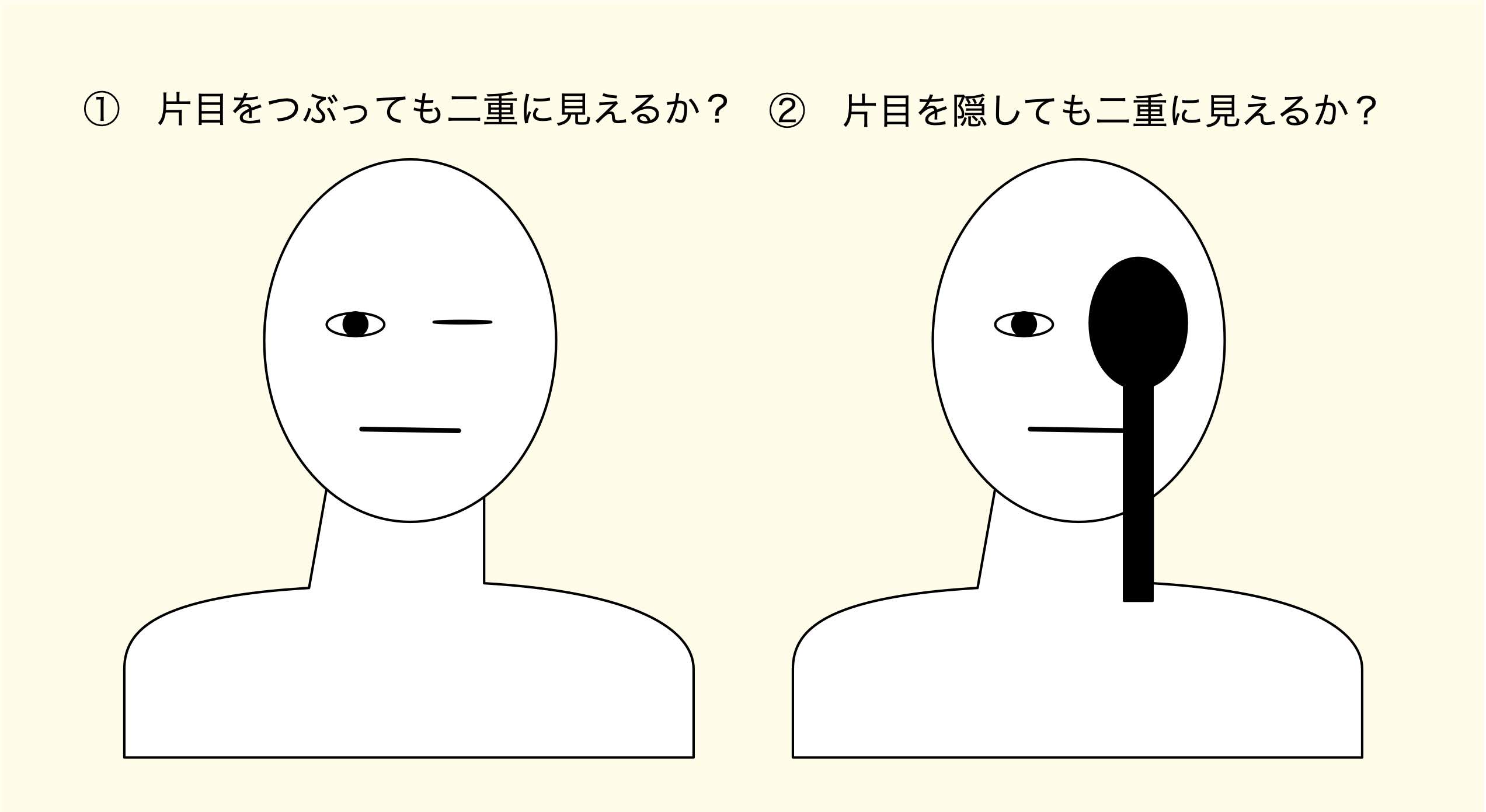
【STEP2】緊急性の高い疾患の検討
★ 複視では積極的に脳CT、脳MRI,MRAを撮影してよい。突発性なら必ず行う
(脳動脈瘤)
-
・緊急性の高い複視の原因疾患の代表は脳動脈瘤で、疑われる場合は速やかに脳神経外科に紹介する
・切迫破裂の場合は速やかに緊急手術が必要 ・内頚動脈ー後交通動脈分岐部の動脈瘤による動眼神経麻痺が生じる
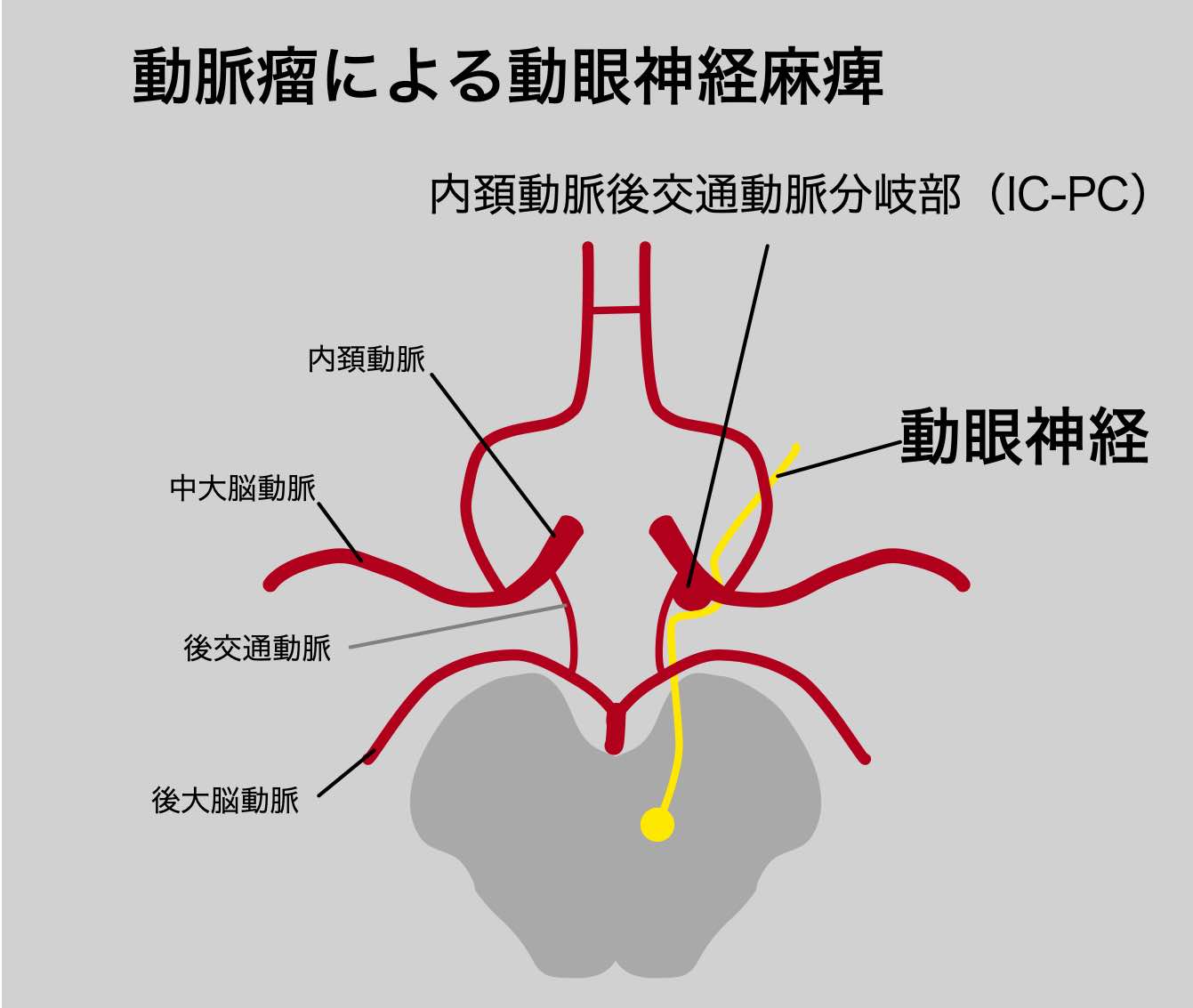
・動眼神経麻痺の6%が脳動脈瘤が原因であったという報告がある(*5)
・動眼神経には副交感神経線維が含まれており、圧迫で散瞳が合併することがある
(内頚動脈海綿静脈洞瘻)
-
・内頚動脈から海綿静脈洞に出血すると、典型的には眼球突出、拍動性雑音、結膜充血の3徴が出現する
・失明、脳出血などを続発する場合がある
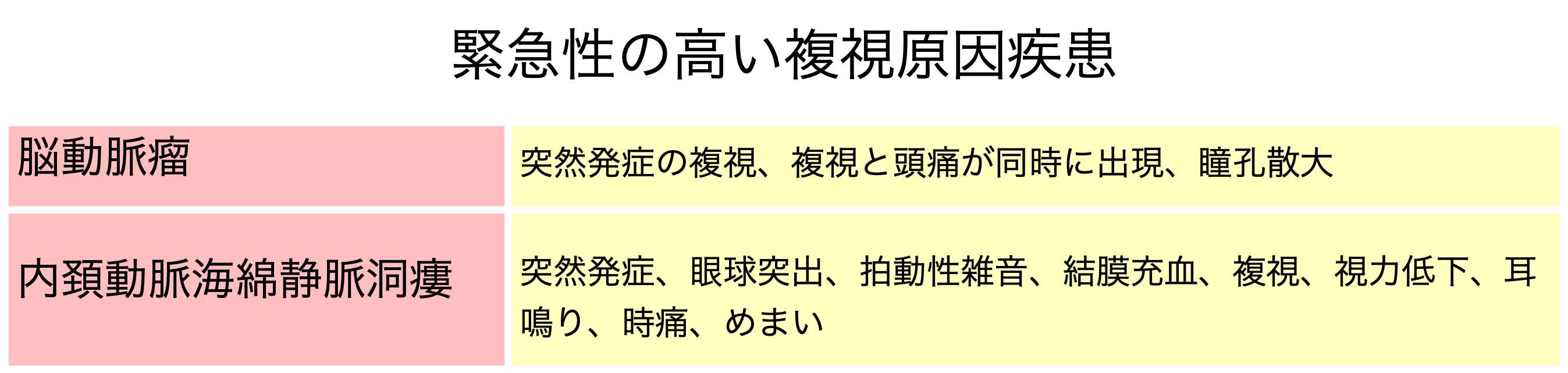
【STEP3】眼球運動の評価
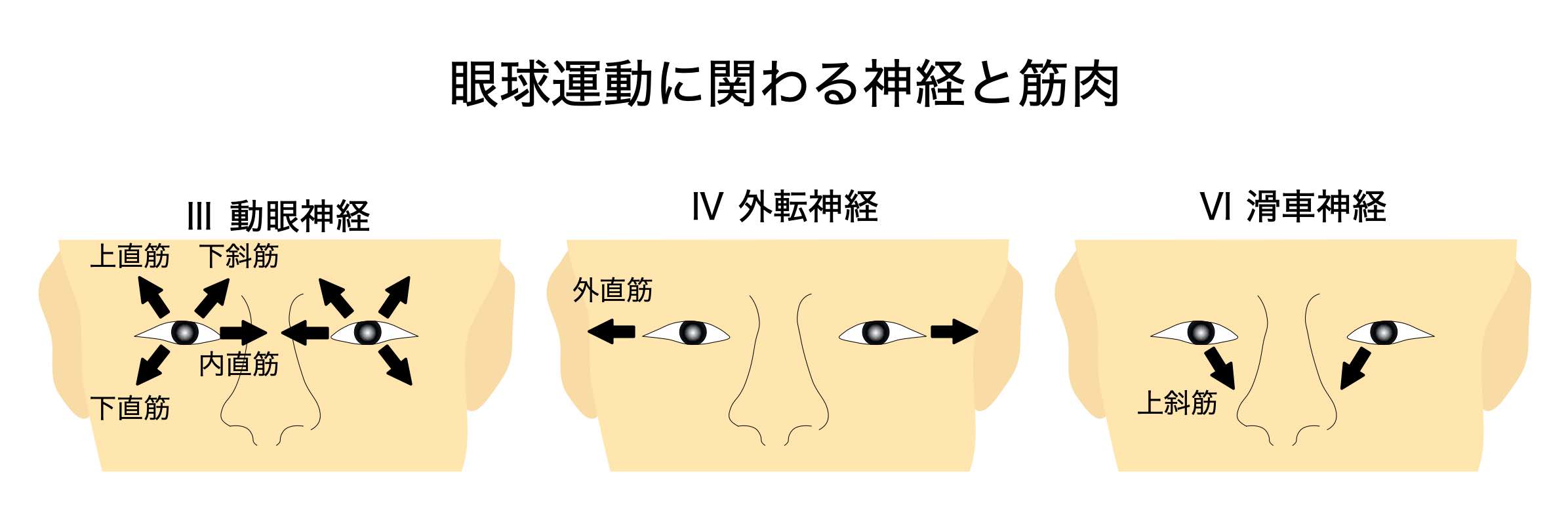
① 眼位
・まず、何も指示を与えない状態で観察する(斜視)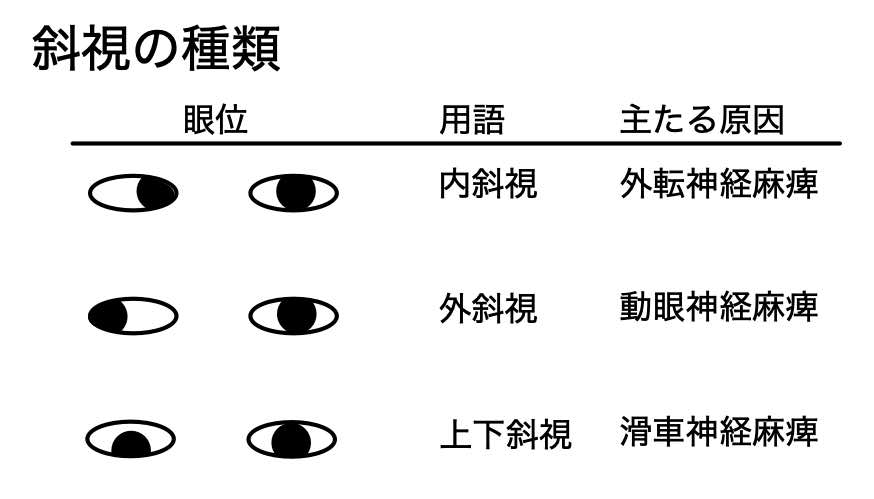
・また、複視がどのように並ぶかを確認する
横に並べば、内転または外転障害(外転神経またはMLF症候群)
縦に並べば上斜筋障害(滑車神経)
斜めに並べばそれ以外の眼筋(動眼神経)を考える
・動眼神経麻痺では眼瞼下垂や散瞳を伴うことがある
② 6方向への指標を用いた眼球運動評価
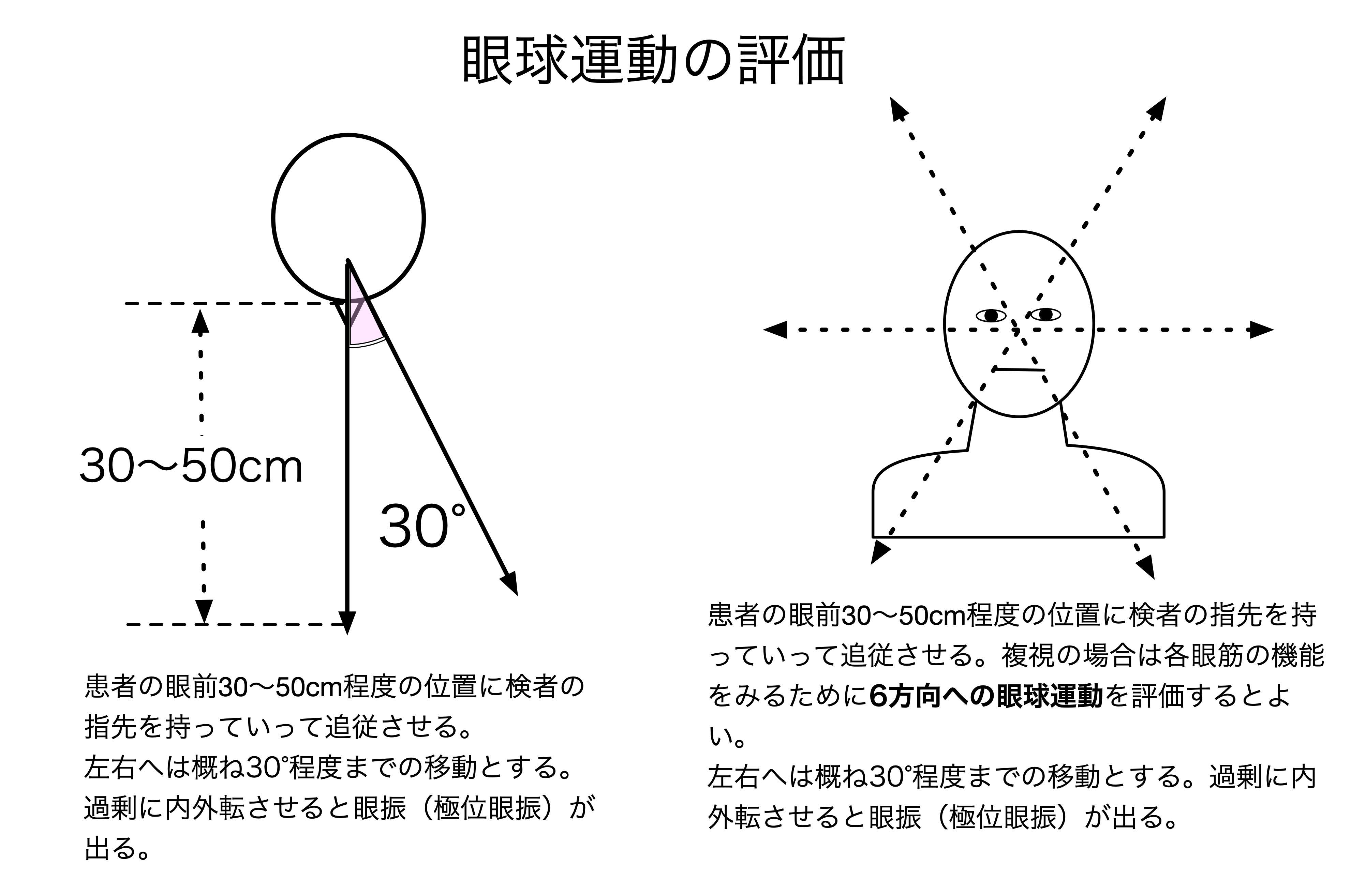
・追視で異常があれば以下のように考えられる
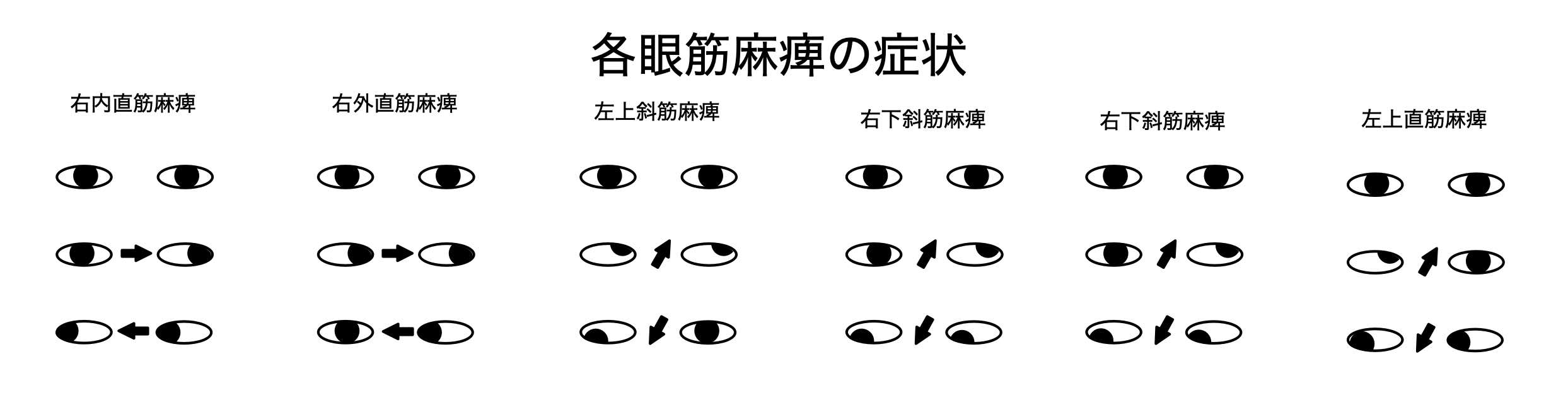
・ただし、随意眼球運動では複視は抑制される傾向があるため、この評価だけでは不十分
③ 輻輳
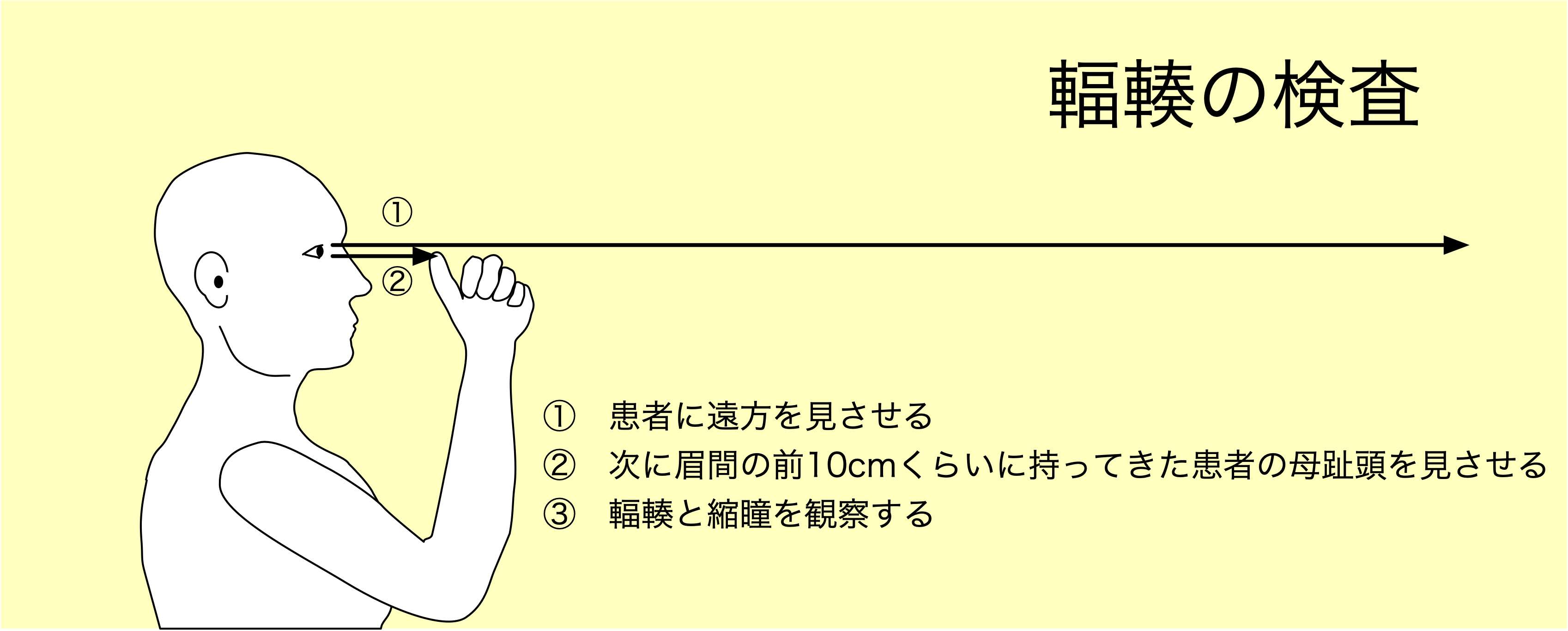
・遠方視で複視が増強する場合は外直筋が、近い部位をみると増強すれば内直筋の異常を考える
④ とくに焦点を合わせないようにしてぼんやりと前をみる
・随意的にものを見ることをやめると、斜視が明かになる場合がある
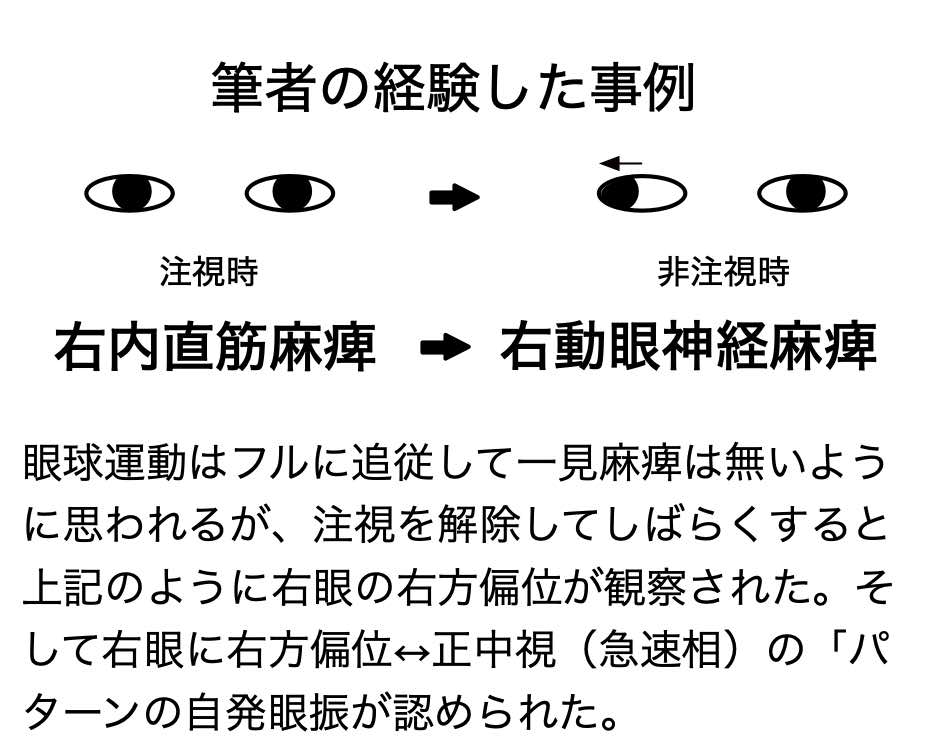
⑤ 複視が増強する眼球運動の方向を確認する
・6方向への眼球運動を行いながら複視が増強する方向を確認する
・眼球運動障害がある方向を注視すると複視が増強する場合が多い
【STEP4 他の症候や脳神経障害の合併】
-
・重症筋無力症(眼筋型)では、複視の症状の強さが日内変動し、夜間や疲労時に悪化する
・甲状腺眼症では眼瞼挙上気味となる
重症筋無力症
バセドー病
・眼筋麻痺のパターンと他の神経徴候の組み合わせにより、ある程度は鑑別診断を推定することが可能
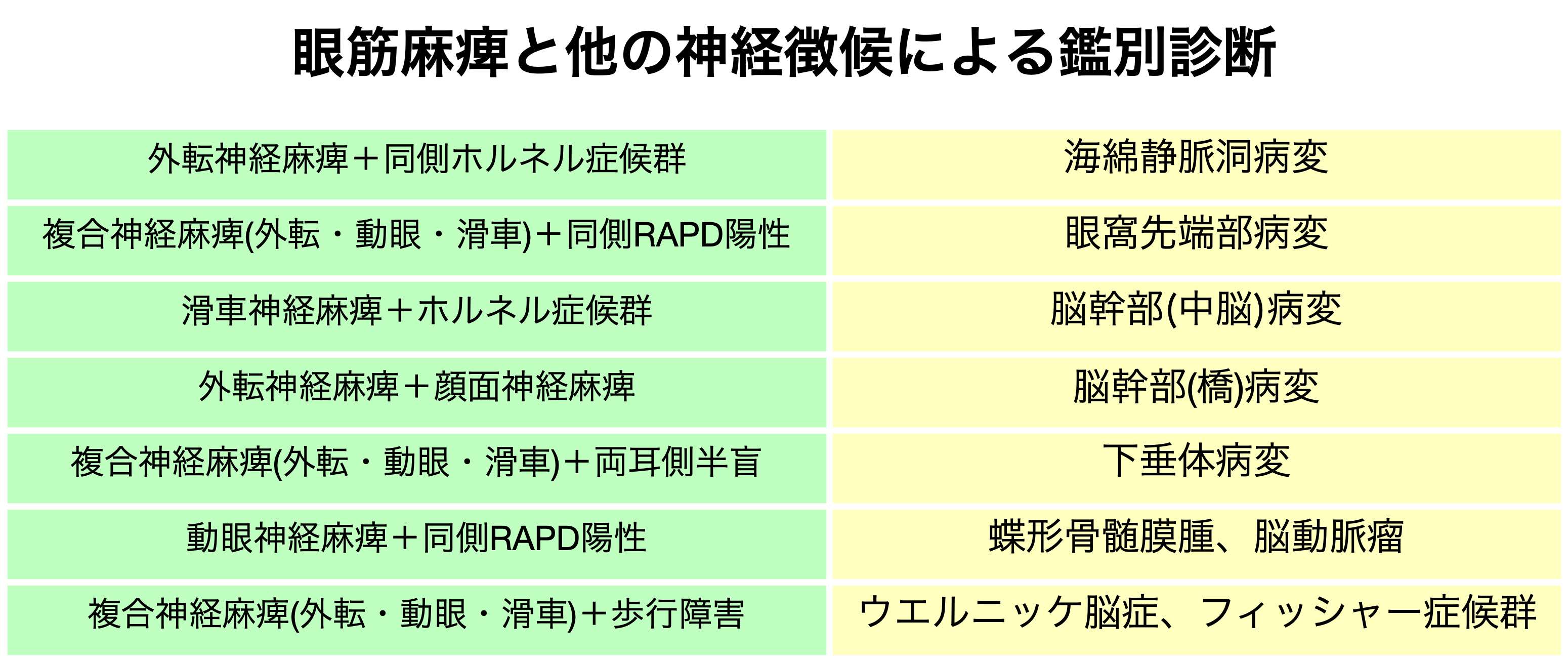
* RAPD(relative afferent pupillary defect: 相対的視覚入力瞳孔障害) 神経眼科にて専用の装置を用いて測定する
** ホルネル症候群 中等度縮瞳、眼瞼下垂、眼球陥凹を3大徴候とする症候群。他に、顔面発汗や潮紅が見られることもある。交感神経遠心路の障害で生じる
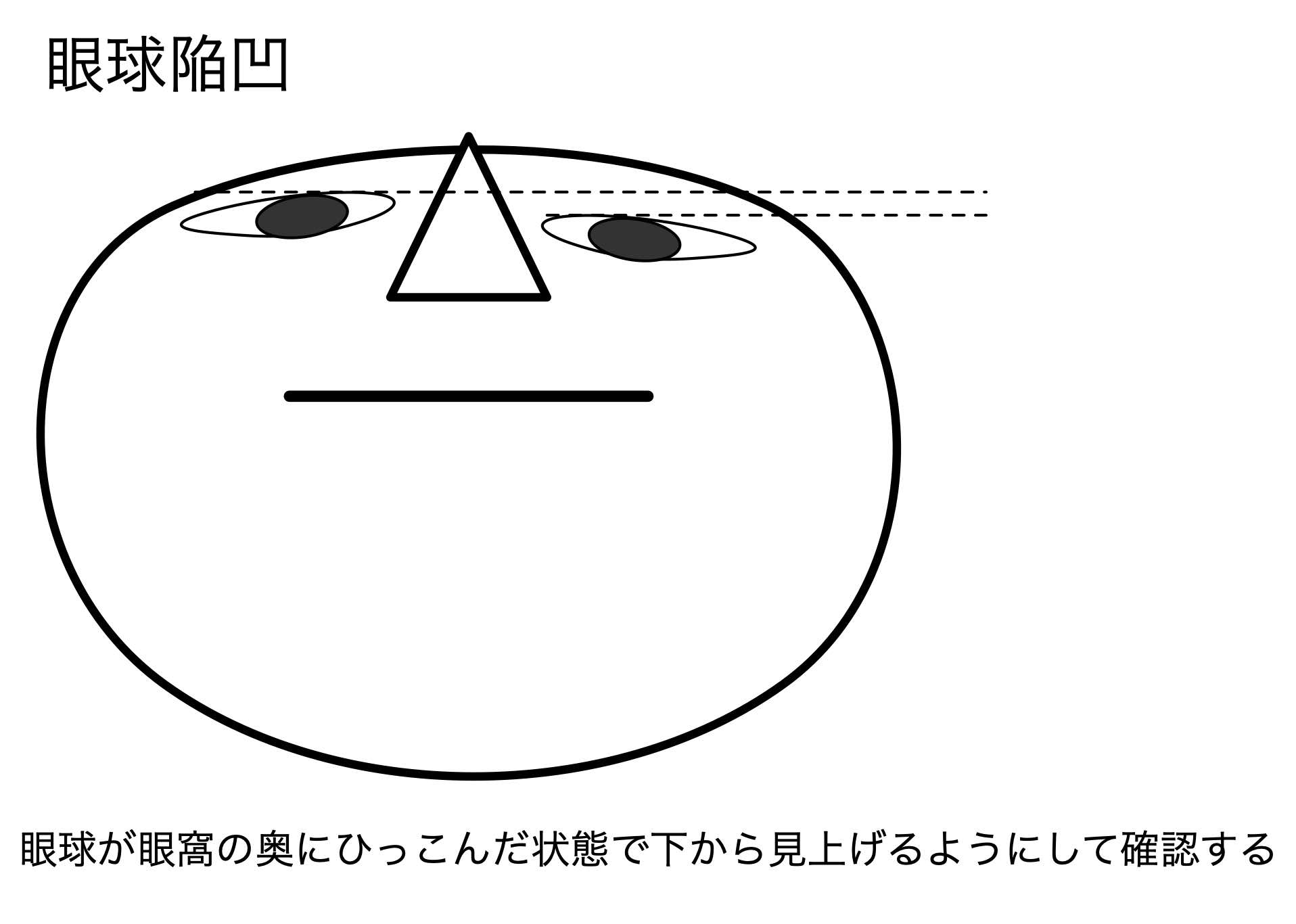
-
・Wernicke脳症では精神運動抑制または無関心、眼振、運動失調、眼筋麻痺、意識障害がみられ,無治療では昏睡状態となって死亡する
・フィッシャー症候群は急性の外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失を三徴とする免疫介在性ニューロパチー
ウエルニッケ脳症
フィッシャー症候群
・MLF症候群は動眼神経麻痺との鑑別が重要
・One-and-a-half症候群では水平眼球運動としては片側の内転しかできなくなる
MLF症候群
One-and-a-half症候群
-
参考文献)
1. 杉田洋一郎「研修医のための内科診療ことはじめ」2022 羊土社
2. 石井義洋「卒後20年総合内科医の診断術 Ver.3」第3版 中外医学社 2024
3. 小黒 浩明 他「複視とめまい」日内会誌 103:486~491,2014
4. 鈴木利根「複視を自覚して来院されたら」日本視能訓練士協会誌 第45巻(2016)
5. Chengbo Fang et.al. Incidence and Etiologies of Acquired Third Nerve Palsy Using a Population-Based Method JAMA Ophthalmol. 2017 Jan 1;135(1):23-28.