糸球体腎炎
- 2017年の透析導入患者の原疾患の内訳は慢性糸球体腎炎が16.3%を占め、42.5%の糖尿病性腎症に続いて第2位
- 本邦では検診システムがあるため、比較的早期の段階に診断がされやすい
- 高齢者の腎炎やネフローゼ症候群が多い
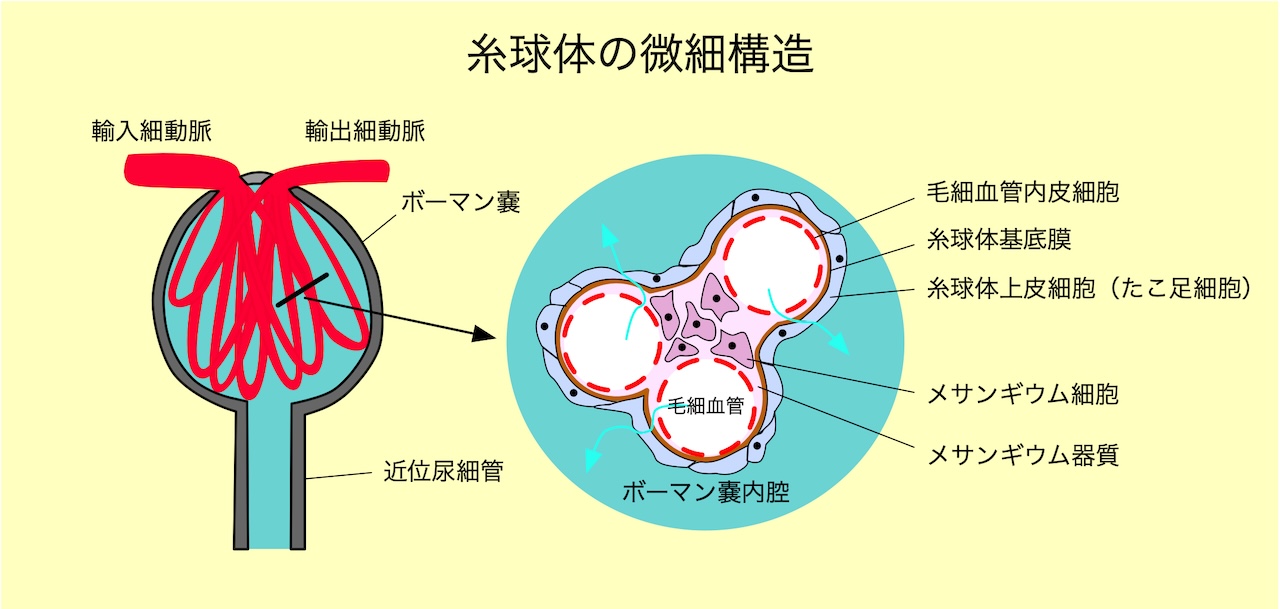
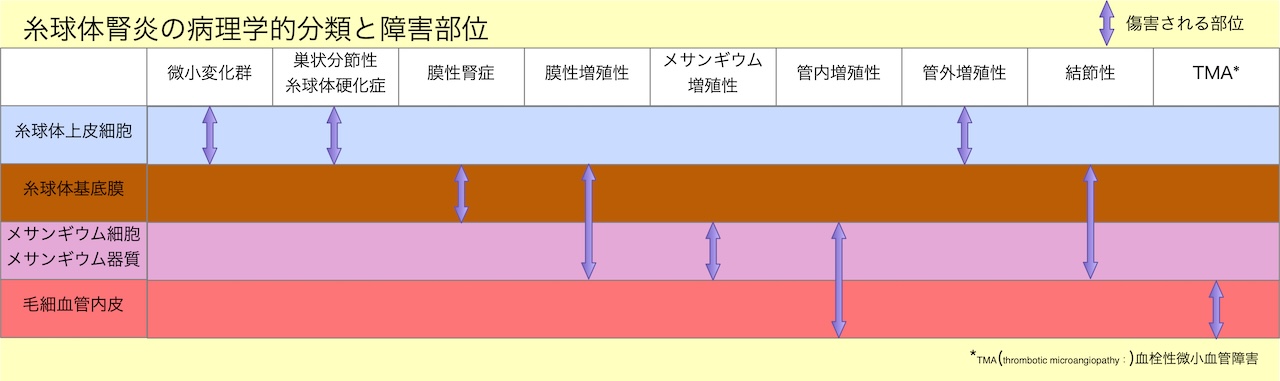
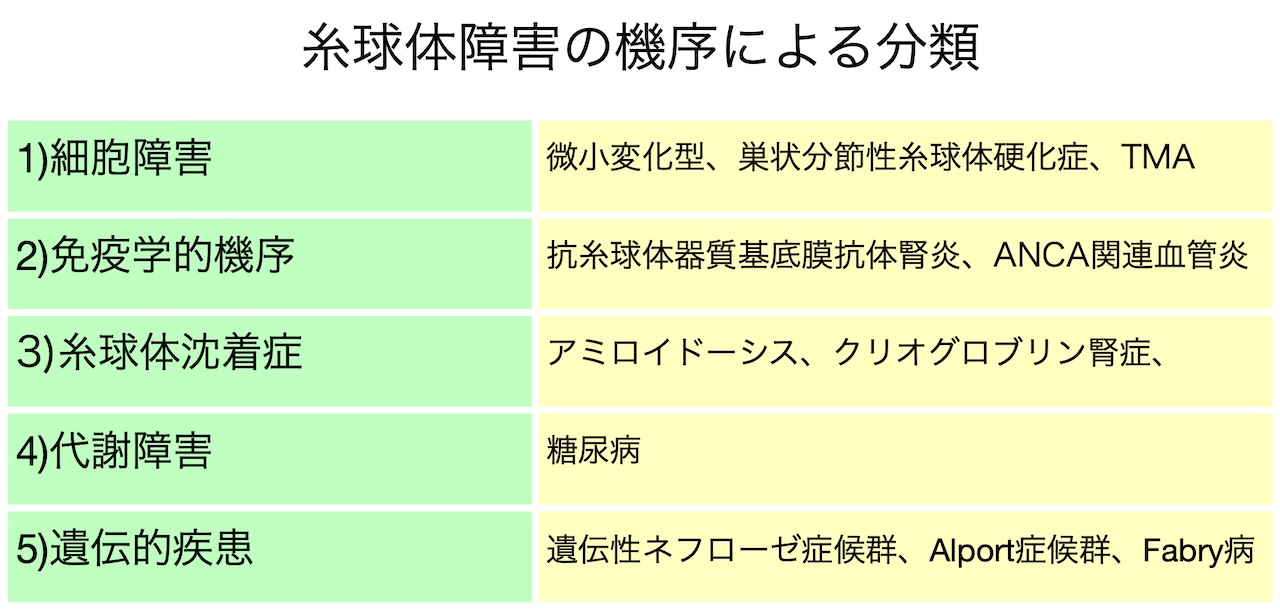
- 参考文献)
- 丸山彰一 他「糸球体腎炎・ネフローゼ症候群の診断と治療の進歩」日内会誌 109:877~880,2020
- 小松康宏「腎臓病診療に自信がつく本」カイ書林 2010
- 姚建 他「糸球体メサンギウム細胞の細胞特性」日腎会誌 2008;5(0 5):554-560.
- 淺沼克彦 他「腎糸球体上皮細胞の細胞特性I」日腎会誌 2008;5(0 5):532-539
- 髙岸勝繁 他「ホスピタリストのための内科診療フローチャート第2版」シーニュ 2019